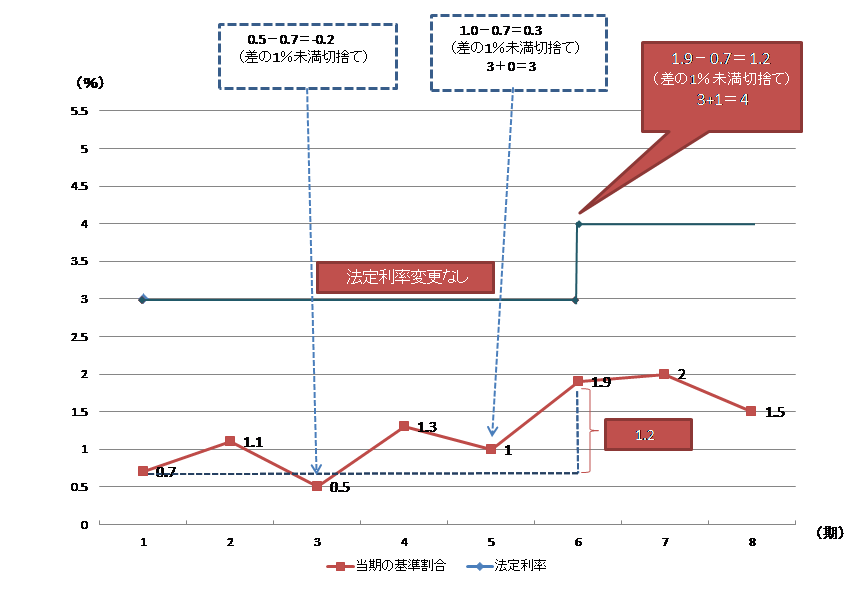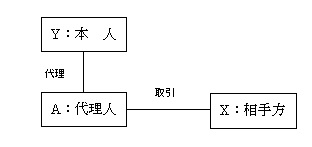今回は、「契約の解除」、「危険負担」、「受領遅滞」に関する改正について説明します。
第1 契約の解除についての改正
契約の解除については、①契約の解除の要件、②原状回復義務の範囲及び③解除権の消滅について改正が行われました。
1 契約の解除の要件の改正
(1) 債務不履行があれば債務者に帰責事由がない場合でも契約の解除をできることとしたこと
まず、個別の契約の解除の要件の改正について説明する前に、全体的な契約の解除の要件に関する改正について説明します。
|
第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条の規定による解除をすることができない。
|
ア 改正点
|
改正法では、債務不履行があれば債務者に帰責事由がない場合にも契約の解除をすることができることとし、例外的に、債権者に帰責事由がある場合にのみ契約の解除をすることができないこととしました。
|
イ 説明
現行法では、債務不履行があった場合でも債務者に帰責事由がないときは、債権者は契約の解除をすることができない(履行不能による解除については明文の定めがあります〔現行法543条〕)ものと解されていました。
しかし、このように解すると、債権者は、天災等の不可抗力によって債務者において債務を履行する見込みが立っていない場合でも、契約を解除して他の取引先と契約をする等の対応に躊躇せざるを得ない事態が生じていることが指摘されていました。
また、解除制度の意義は、債務の履行を怠った債務者に対する制裁ではなく、債権者を契約の拘束力から解放することにあると理解すれば、債務者に帰責事由があることは理論的にも解除のための必須の要件ではないと考えられます。
そこで、改正法では、債務不履行があれば債務者に帰責事由がない場合でも、契約の解除をすることができることとされました。
他方で、債務不履行について債権者に帰責事由がある場合にまで債権者を契約の拘束力から解放することを認めれば、債権者が故意に債務の履行を妨げて契約の拘束力から免れることが可能となってしまい、信義則・公平の観点から相当ではありません。そこで、改正法は、債権者に債務不履行について帰責事由がある場合には、例外的に、契約の解除をすることができないものとしました(改正法543条。なお、現行法543条ただし書は削除され、現行法543条本文において規定されていた内容は、改正法542条1項1号及び2項1号として定められています。)。
なお、改正法においては、債務不履行についての帰責事由は、①債権者にある場合、②債務者にある場合及び③双方にない場合のいずれかであることを前提に整理されており、実際には、債務不履行についての帰責事由が双方にあるというケースも考えられますが、その場合でも、その原因や寄与の度合いに応じて、①~③のいずれかに振り分けることとされています(筒井健夫=村松秀樹『一問一答 民法(債権関係)改正』235頁(注3)〔商事法務、2018〕)。
(2) 催告による解除(催告解除)について、債務不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」には、債権者は契約の解除をすることができないこととしたこと
|
第541条(催告による解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
|
ア 改正点
|
改正法では、現行法541条を維持した上、ただし書として、催告後相当期間経過時における債務不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」には、債権者は契約の解除をすることができない旨の規定を加えました。
|
イ 説明
現行法541条(履行遅滞等による解除。なお、改正法541条では、見出しが、「履行遅滞等による解除」から「催告による解除」と改正されました。)においては、債務不履行を理由とする契約の解除をするために必要な債務の不履行の程度を定める規定はありませんが、判例(大判昭和14年12月13日判決全集7輯4号10頁、最判昭和36年11月21日民集15巻10号2507頁等)は、不履行の部分がわずかな場合や契約の目的を達するために必須とは言えない付随的な義務の不履行の場合には、契約の解除を制限していました。
そこで、改正法では、催告解除の要件を具体化する観点から、判例の基本的な考え方を前提に催告解除が制限される要件を明文化しました。
具体的には、現行法541条に、ただし書として、催告後相当期間経過時における債務不履行が「契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」には、債権者は契約の解除をすることができない旨の規定を加えました。
◆「軽微」の判断方法について
債務不履行が「軽微」であるかどうかは、解除の対象とされた「契約及び取引上の社会通念」に照らして判断するものとされており、契約書の文言のみならず当該契約に関する一切の事情をもとに、当該契約についての取引上の社会通念をも考慮して、総合的に判断されることになります。
そのため、たとえば、ある製品の制作のために必要な部品を供給する契約において、債務者が納品した部品の数量の不足が僅かであったとしても、不足分が当該製品の制作のために必要不可欠な場合には、「契約及び取引上の社会通念」に照らして「軽微」とはいえないとされることもあり得ます(筒井=村松・前掲236頁(注1))。
◆「軽微」の判断基準時について
債務不履行が「軽微」であるかどうかの判断基準時は、催告後相当期間経過時です。そのため、債権者が債務の履行を催告した時点の債務不履行の程度が軽微とは言えない場合でも、その後、債務者が一部履行をした等により、相当期間経過時には債務不履行の程度が軽微と判断される場合には、解除が認められないということも考えられます(日本弁護士連合会『実務解説 改正債権法』126頁〔弘文堂、2017〕。
(3) 催告によらない解除(無催告解除)について要件を整理したこと
|
第542条(催告によらない解除)
1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
|
ア 改正点
|
改正法では、現行法で無催告解除が明文で認められている定期行為の履行遅滞による解除(現行法542条)及び履行不能による解除(同法543条)に加えて、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき、債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき及びこれらのほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるときにも、無催告で契約の全部の解除をすることができることとしました。
また、債務の一部の履行が不能であるとき及び債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときには、無催告で契約の一部の解除をすることができることとしました。
|
イ 説明
現行法では、債務不履行による契約の解除については、原則として催告を要するとしたうえで、定期行為の履行遅滞(現行法542条)及び履行不能(現行法543条)の場合のみ、明文で催告を要しないとしていました。
これは、催告により改めて債務者に履行の機会を与えても、債務者は履行をすることができないか、債務者が履行をしても契約の目的を達成されることがないという趣旨によるものですが、このような趣旨に鑑みれば、現行法に明文の定めがある場合のみならず、債務者に履行の機会を与えても無意味な場合には、無催告解除を認めるのが合理的です。
そこで、改正法では、無催告解除の要件を整理し、以下のとおり、定期行為の履行遅滞(改正法542条1項4号)及び履行不能(同項1号)の場合のみならず、無催告解除が認められる場合を具体的に定めました。
①債務の全部の履行が不能であるとき(改正法542条1項1号)。
②債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号)。
③債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号)。
④契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達成することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき(同項4号)
⑤これらのほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号)。
また、上記は契約の全部の解除が認められる場合ですが、改正法は、以下の場合には、無催告で契約の一部を解除することができることとしました。
①債務の一部の履行が不能であるとき(同条2項1号)。
②債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号)。
なお、改正法542条1項3号は、履行の一部に不能がある場合でも契約の全部を解除することができることを定めたものです。
◆改正法542条1項5号が適用される対象
改正法542条1項5号が適用される対象は、同項1号から4号には該当しないが、「債務の不履行それ自体によりもはや契約をした目的を達することができないと評価されるため催告要件を課すこと自体が不適切である場合」とされており、例えば、大型機材を用いたビルの清掃業務の委託契約において、債務者の従業員がその不注意によってビル内の人に大怪我を負わせた場合等が想定されています(部会資料68A・24頁)。
また、債務について不完全履行がされたが、その履行の追完は不能である場合は、現状以上の状態になることは客観的に想定されないため、その状態の程度によっては、改正法542条1項5号に該当するものとして、無催告解除をすることができるものと考えられます。
なお、このように考えると、不完全履行ではあるが契約の目的を達成することができる場合に契約の解除をしようとするときは本条によることができないため、改正法541条により、追完が不能であるのに催告をして契約を解除しなければならないという不合理な状態が生じるようにも思われますが、その場合には、そもそも債務不履行の程度が「軽微」なものとして、催告解除自体が許されないと考えられます(筒井=村松・前掲239頁(注2))。
2 原状回復義務の範囲についての改正
|
第545条(解除の効果)
1 (現行法1項と同じ。)
2 (現行法2項と同じ。)
3 第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4 (現行法3項と同じ。)
|
(1) 改正点
|
現行法545条1項に基づく原状回復義務により金銭以外の物を返還するときも、その受領の時以後に生じた果実を返還しなければならないことを条文上明記しました。
|
(2) 説明
現行法541条2項は、同条1項に基づく原状回復義務により金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない旨を定めていましたが、金銭以外の物を返還するときの果実の返還については明文の定めはありませんでした。
しかし、通説は、金銭以外の物を返還するときもその受領の時以後に生じた果実を返還しなければならないと解していたため、改正法では、その趣旨を条文上も明記することとしました。
3 解除権の消滅についての改正
|
第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)
解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りではない。
|
(1) 改正点
|
解除権を有する者の解除権が消滅する場合を定めた現行法548条1項を維持しつつ、ただし書として、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは解除権が消滅しない旨の規定が新設されました。また、これに伴い、契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は消滅しない旨を定めた現行法548条2項は削除されました。
|
(2) 説明
現行法548条1項は、解除権者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、又は返還することができなかった等の場合に、解除権が消滅する場合を定めていました。その趣旨は、同項に定める場合は、解除権者は解除権を黙示に放棄したといえることや解除による原状回復として契約の目的物を従前の状態で返還することができないのに、解除を認めると相手方との公平を害することにあるとされていました。
しかし、解除権者が解除権を有することを知らない場合にまで、解除権を黙示に放棄したと評価するのは相当ではないこと、また、目的物を著しく損傷等した場合には、解除権者は解除による原状回復として目的物の価額を償還する義務があると解され、解除を認めても相手方との公平をそれほど害するとは言えないことから、同項の規律を変更することが検討されました。
そこで、上記を踏まえ、現行法548条1項の規定を維持しつつ、ただし書として、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは解除権が消滅しない旨の規定が新設されました。
また、現行法548条2項は、同条1項の要件を充足しない場合の一場面のみを取り出したものにすぎないため、解釈上、無用の混乱を招きかねないとして削除されました。
第2 危険負担に関する改正
危険負担については、①債権者主義を定めた規定(現行法534条、535条)の廃止、②危険負担の効果について改正が行われました。
1 債権者主義を定めた規定の廃止
(1) 改正点
|
改正法では、特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときに、債務者が反対給付を失わない(債権者主義)旨を定めていた現行法の規定(現行法534条及びこれに関連する535条)を削除しました。
|
(2) 説明
現行法は、危険負担について債務者主義を原則とし(現行法536条1項)、他方で、特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは債務者は反対給付を失わない旨を定める等(現行法534条1項、535条1項・2項)して、例外的に債権者主義を採用していました。
しかし、債権者主義を定めた現行法534条1項によれば、たとえば、建物の売買契約の締結直後にその建物が地震によって滅失した場合にも買主はなお代金を支払う必要がありますが、目的物の引渡しも受けず、自己の支配下に置いていない買主(債権者)に過大なリスクを負わせるものであって不当であるという批判が強くなされていました。また、債権者主義の根拠は、契約締結後に目的物の価格が高騰等した場合の利益を債権者は受けることができるのであるから、目的物の滅失等による損失も債権者が負担すべきである等と説明されていたが、両者は次元の異なる問題であって、比較すべきではないとされていました。
そこで、改正法では、債権者主義を定めた規定(現行法534条及びこれに関連する535条)を削除しました。
改正法の下では、債権者主義を定めた規定の削除によって、従前、現行法534条及び535条が適用されていた場面でも、536条により規律されることになります。
ただし、特定された目的物の滅失等についての危険の移転については、売買に関する改正法567条(同条は性質の許す限りにおいて有償契約に準用されます〔改正法559条〕)が新設されており、この改正法567条によって規律されることになります。)
2 危険負担の効果に関する改正
|
第536条(債務者の危険負担等)
1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
|
(1) 改正点
|
改正法では、危険負担の効果について、現行法の定める反対給付債務の消滅から、反対給付債務の履行拒絶権の付与と改められました。
|
(2) 説明
現行法536条1項は、危険負担の効果について、当事者双方の帰責事由によらずに債務者の債務が履行不能となったときは、債権者の反対給付債務も消滅する旨を定めていました。
しかし、改正法では、債務者に帰責事由がなくとも、債権者は契約の解除をすることができることとされたため(改正法541~543条)、現行法536条1項をそのまま維持すると、契約の解除によって債権者は自己の反対給付債務を負わないこととなる一方で、危険負担によって債権者の反対給付債務は当然に消滅することになり、制度の重複が生じることになってしまうことになりました。そのため、危険負担の制度は廃止することも検討されましたが、債権者は、現行法においては反対給付債務が当然に消滅していた場面においても、解除の意思表示をしなければならず、実質的な負担を増加させるおそれがあること及び複数の債権者の全員による解除権の行使が必要とされる場面(現行法544条)において、債権者の1名が行方不明等の場合には、解除権の行使が事実上困難となるという不都合も生じ得ます。
そこで、改正法536条1項では、危険負担の効果を、反対給付債務の消滅から、反対給付債務の履行拒絶権の付与に改めました。
これにより、債権者は、債務者に帰責事由がない場合には、危険負担に基づき、反対給付債務の履行を拒むことができる上、契約の解除により、反対給付債務を確定的に消滅させることができることとなりました。
なお、改正法536条2項について、同条1項の上記改正に伴い、字句の修正が行われています。
上記に関する改正法と現行法の扱いを整理すると、下記の表(日本弁護士連合会・前掲141頁から引用の上、一部記載を変更)のとおりとなります。
|
履行不能の原因
|
改正法
|
現行法
|
|
当事者双方に帰責事由なし
|
・債権者の反対給付債務は、当然には消滅しない。ただし、債権者は、履行を拒絶することができる(本条1項)。
・債権者が反対給付債務を消滅させるためには、契約の解除をする必要がある(改正法542条1項1号)。
|
・債権者の反対給付債務は当然に消滅する(現行法536条1項)。
・債権者は、契約を解除する必要はない。
|
|
債権者に帰責事由あり
|
・債権者の反対給付債務は消滅せず、債権者は、履行を拒絶することができない。ただし、債務者は、自己の債務を免れたことによって得た利益を債権者に償還する必要がある(改正法536条2項後段)
|
・同左(現行法536条2項)
|
|
債務者に帰責事由あり
|
・債権者の反対給付債務は、当然には消滅しない。
・債権者が反対給付債務を消滅させるためには、契約の解除をする必要がある(改正法542条1項1号)。
|
・同左(現行法543条本文)
|
◆雇用契約において、使用者の責めに帰すべき事由により労働者が労務を提供できなくなった場合の労働者の使用者に対する賃金請求と改正法536条2項の関係
改正法536条2項においては、債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときについて、現行法536条2項に定める「債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」との文言から「債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」との文言に改正されています。しかし、これは、危険負担の効果を履行拒絶権の付与と改めた改正法536条1項の改正に伴って字句を修正したものにすぎません。
そのため、現行法536条2項を根拠として、雇用契約において労働者が使用者の責めに帰すべき事由により労務の提供ができない場合、労働者は、労務の提供がないとしても、使用者に対して、賃金債権の履行を請求することができるとの解釈は、改正法の下でも維持されるものと解されています(筒井=村松・前掲229頁)。
第3 受領遅滞についての改正
|
第413条(受領遅滞)
1 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
|
|
第413条の2(履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
1 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす
|
(1) 改正点
|
改正法413条1項・2項及び413条の2第2項において、判例及び一般的な解釈に従って認められている受領遅滞の3つの効果が明文化されることになりました。
|
(2) 説明
受領遅滞の効果については、様々な議論があるものの、判例及び一般的な解釈によれば、次の3つの効果が認められているところ、現行法413条は「遅滞の責任を負う。」とのみ定めており、この文言から、これらの効果を読み取ることは困難でした。
(受領遅滞の効果)
①特定物の引渡債務の債務者は、受領遅滞となった後は、善管注意義務(改正法400条)ではなく、自己の財産に対するのと同一の注意をもって目的物を保存すれば足りる。
②受領遅滞により増加した債務の履行費用は、債権者の負担となる。
③受領遅滞となった後に当事者双方の責めに帰すことができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
そこで、改正法413条1項・2項及び413条の2第2項では、これらの受領遅滞の効果を明文で定めることとされました。
なお、改正法413条の2第1項は、受領遅滞ではなく履行遅滞の場合の規定であり、債務者が履行遅滞である場合に当事者双方の責めに帰すことができない事由によってその債務の履行が不能となった場合には、その履行の不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなすものです。
◆受領遅滞について債権者に帰責事由がない場合の受領遅滞の効果の有無
受領遅滞について債権者に帰責事由がない場合にも、上記の受領遅滞の効果が生じるかどうかは、改正法の下でも引き続き解釈に委ねられますが、判例(最二小判昭和40年12月3日民集19巻9号2090頁)は、受領遅滞と債務不履行とは別であるとしているため、債権者に帰責事由がない場合でも受領遅滞の効果が発生するとの立場であると解されています(筒井=村松・前掲73頁)。
◆受領遅滞に基づく債務者の損害賠償請求及び契約の解除の可否
受領遅滞に基づいて、債務者が債権者に対して損害賠償請求や契約の解除をすることができるかどうかについては、改正法の下でも引き続き解釈に委ねられますが、判例(前掲・最二小判昭和40年12月3日)は、基本的に、損害賠償請求や契約の解除をすることはできないと解しています(筒井=村松・前掲73頁)。
(弁護士 小林 隆彦)